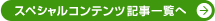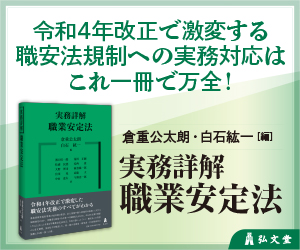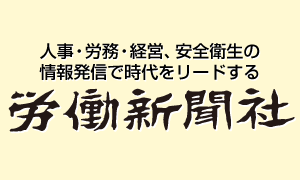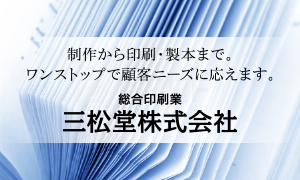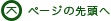解決金の高騰を招く可能性もある解雇の金銭的解決
歴史は繰り返す。解雇の金銭的解決をめぐる議論も、その例外ではない。
(第156回国会に関係法案提出)
2003年3月28日に閣議決定された「規制改革推進3か年計画(再改定)」には、「労働基準法の改正等」(新しい労働者像に応じた制度改革)の一環として、このような措置内容が記される。
 その結果、解雇ルールの立法化については、2003年の法改正により、労基法18条の2に「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」との定めが置かれることになった(04年1月1日施行。その後、労働契約法の制定に伴い、2008年3月1日には同法16条に移行)ものの、後段の「金銭賠償方式」という選択肢の導入については、結局、労使双方の賛成が得られず、その試みが頓挫することになる。
その結果、解雇ルールの立法化については、2003年の法改正により、労基法18条の2に「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」との定めが置かれることになった(04年1月1日施行。その後、労働契約法の制定に伴い、2008年3月1日には同法16条に移行)ものの、後段の「金銭賠償方式」という選択肢の導入については、結局、労使双方の賛成が得られず、その試みが頓挫することになる。
ただ、具体的な検討が進んでいなかった、というわけでは必ずしもない。
例えば、2003年2月10日に開催された労働政策審議会労働条件分科会には、厚生労働省から、次のような内容からなる「労働基準法の一部を改正する法律案について(検討の内容)」が示されている。
2 判決等による労働契約の終了
(1)労働者は、判決で解雇が無効であることが確定した場合において、当該労働者が職場復帰したとしても、労働契約の本旨に従った義務を履行することが困難となる状況が生ずることが明らかであるときは、退職と引き換えに、当該解雇を行った使用者に対して補償金の支払を請求することができるものとすること。
(2)使用者は、判決で解雇が無効であることが確定した場合において、次のいずれにも該当する事情があるときは、労働者との間の労働契約の終了を裁判所に請求することができるものとすること。
ア 使用者の行った解雇が、その使用する労働者の解雇に関する権利を制限するこの法律若しくは他の法律の規定に反しないもの、かつ、公序良俗に反しないものであること。
イ 使用者と労働者との間に当該労働者の職場復帰に関する紛争が生じている場合であって、当該労働者の言動が原因となって、当該労働者が職場復帰したとしても、職場の秩序又は規律が維持できず、当該労働者又は当該事業場の他の労働者が労働契約の本旨に従った義務を履行することが困難となることが明らかであること。
ウ 補償金の支払を約すること。
(3)補償金の額は、平均賃金の○日分とするものとすること。
(4)使用者による補償金の支払は、労働者の使用者に対する損害賠償の請求を妨げないものとすること。
そして、上記の厚労省案が空欄(○日分)としていた補償金の額については、東京商工会議所が当時、次のような調査結果を公表していたことが注目される(「平成15年度労働政策に関するアンケート調査」。2003年6月実施。調査対象は、東商労働委員会関係企業、議員・支部役員企業、計1601社)。
【解雇無効の場合に労働契約を終了させるために使用者が支払うこととなるいわゆる「解決金」の額】
| 前提条件(勤続年数) | 有効回答数 | 平均月数 |
| 仮に一律に定めるとした場合 | 235社 | 4.5ヶ月 |
| 勤続5年未満 | 222社 | 2.6ヶ月 |
| 勤続5年以上10年未満 | 222社 | 4.1ヶ月 |
| 勤続10年以上20年未満 | 222社 | 6.2ヶ月 |
| 勤続20年以上30年未満 | 222社 | 7.8ヶ月 |
| 勤続30年以上 | 222社 | 8.8ヶ月 |
東商の調査結果には、中小企業の声が反映されていると思われるが、この調査結果からもわかるように、中小企業の想定する(妥当と考える?)解決金の額は、その支払能力を反映してか、総じて低い額にとどまっている。
また、金銭解決方式が法制化された場合、解決金が高止まりすることによって、企業が採用そのものに消極的になる可能性も危惧される。この点については、行き過ぎた借地人の保護=立退料の高騰により、かえって土地を貸す者がいなくなった(土地を借りることができなくなった)、かつての借地法の経験が多少とも参考になろう(注1)。
他方、上記の厚労省案は、厳しい制約条件を付した上でのこととはいえ、使用者による金銭解決の申立て(補償金の支払の約束を伴う労働契約終了の請求)をなお認めるものであったが、規制改革会議は現在、労働者による申立てのみを認める姿勢を明確にしており(注2)、使用者側が安易に同調するとは考えにくい状況にある。労使対等の原則(労基法2条)に照らしても、こうした規制改革会議の姿勢には問題があるといえよう。
以上のほか、最低賃金を2016年以降、毎年3%ずつ引き上げ、最賃額を全国加重平均で1000円とすることを政府は目標としている。この水準を既に達成している国も少なからず存在するが、その背景には広い範囲に及ぶ適用除外がある。高校生のアルバイトにまで、1000円の時給を支給しているような国は、世界のどこにも存在しない(注3)。
最低賃金の引上げそのものには、最賃法の改正を必要としないとはいえ、適用除外を実現するためには、やはり法改正が必要となる。そうした現実にも、しかと目を向けるべきであろう。(おわり)
注1:なお、定期借地権(借地借家法22条)の制度は、こうした状況を打開するために、設けられた。以上につき、少し古いものであるが、拙稿「解雇ルール、法制化の動き」『読売新聞』2002年11月8日付け朝刊「けいざい講座」を参照。
注2:例えば、鶴光太郎「労働者に金銭解決の選択肢、解雇紛争処理を多様化へ」『週刊労働新聞』2016年1月4日号を参照。
注3:拙著『労働法改革は現場に学べ!――これからの雇用・労働法制』(労働新聞社、2015年)36-38頁を参照。
小嶌 典明氏(こじま・のりあき)1952年大阪市生まれ。神戸大学法学部卒業。大阪大学大学院法学研究科教授。労働法専攻。小渕内閣から第一次安倍内閣まで、規制改革委員会の参与等として雇用労働法制の改革に従事するかたわら、法人化の前後を通じて計8年間、国立大学における人事労務の現場で実務に携わる。最近の主な著作に『職場の法律は小説より奇なり』(講談社)、『労働市場改革のミッション』(東洋経済新報社)、『国立大学法人と労働法』(ジアース教育新社)、『労働法の「常識」は現場の「非常識」――程良い規制を求めて』(中央経済社)、『労働法改革は現場に学べ!――これからの雇用・労働法制』(労働新聞社)、『法人職員・公務員のための労働法72話』(ジアース教育新社)等がある。