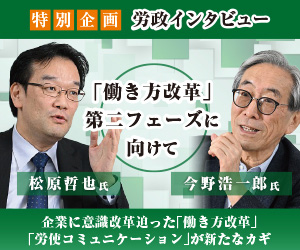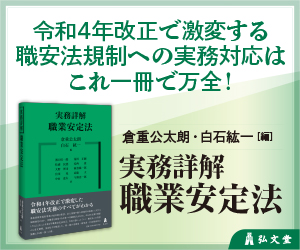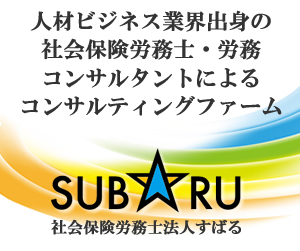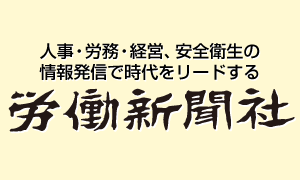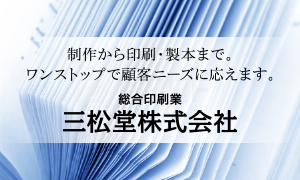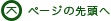厚生労働省は2日、労働者性の判断基準などを検討する有識者会議「労働基準法における『労働者』に関する研究会」を立ち上げた=写真。働き方の変化や多様化が進むなか、労基法上の労働者性に関する裁判例や学説の分析に加え、プラットフォームワーカーを含む「新しい働き方」について調査・分析する。国際的動向も視野に入れながら実態把握のためのヒアリングも実施して議論を深め、「雇用なのか業務委託なのか」の線引きに踏み込む。来年度以降も継続する腰を据えた会議体となる見通しだ。
 昨年12月に報告書を取りまとめた「労働基準関係法制研究会」は、1985年(昭和60年)の「労働基準法研究会」報告が整理した「労基法上の『労働者』の判断基準」に言及。「作成から約40年が経過して働き方の変化・多様化に必ずしも対応できない部分が生じている」と指摘し、総合的な研究の必要性を提言していた。今回、新しく設置した「労働者研究会」はこの提言を受けた対応のひとつで、労働者性の判断基準について掘り下げる。
昨年12月に報告書を取りまとめた「労働基準関係法制研究会」は、1985年(昭和60年)の「労働基準法研究会」報告が整理した「労基法上の『労働者』の判断基準」に言及。「作成から約40年が経過して働き方の変化・多様化に必ずしも対応できない部分が生じている」と指摘し、総合的な研究の必要性を提言していた。今回、新しく設置した「労働者研究会」はこの提言を受けた対応のひとつで、労働者性の判断基準について掘り下げる。
具体的なテーマとして、労働者性に関する事例やプラットフォームワーカーなど新しい働き方の分析に加え、労基法上の労働者性の判断基準のあり方、新たな働き方への対応も含む労働者性判断の予見可能性を高めるための方策なども検討する。また、今後実施する弁護士などへのヒアリングでは、(1)労働者性を争点にした訴訟・労働審判において「昭和60年報告」の内容が判断の参考とされているか(2)判断されていない事例があるとすれば、どのような判断基準による事例があるか(3)司法において労働者性判断が重視している判断要素は何か(4)現場での労働実態(労働態様)と契約上の働き方の内容のどちらが重視される傾向にあるかーーなどを検証していく方針だ。
構成員は芦野訓和氏(専修大学法学部教授)、岩村正彦氏(東京大学名誉教授)、小畑史子氏(京都大学大学院人間・環境学研究科総合人間学部教授)、笠木映里氏(東京大学大学院法学政治学研究科教授)、川田琢之氏(筑波大学ビジネスサイエンス系教授)、 島田裕子氏(京都大学大学院法学研究科教授)、新屋敷恵美子氏(九州大学法学部准教授)、 竹内(奥野)寿氏(早稲田大学法学学術院教授)、水町勇一郎氏(早稲田大学法学学術院教授)――の9人。座長は岩村氏、座長代理は川田氏が務める。
この日は、事務局の厚労省が...
※こちらの記事の全文は、有料会員限定の配信とさせていただいております。有料会員への入会をご検討の方は、右上の「会員限定メールサービス(triangle)」のバナーをクリックしていただき、まずはサンプルをご請求ください。「triangle」は法人向けのサービスです。
【関連記事】
「多様な働き方を支える仕組み」を基軸に報告書策定、労基法巡る有識者研究会
労政審で法改正の議論開始へ(2024年12月24日)