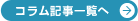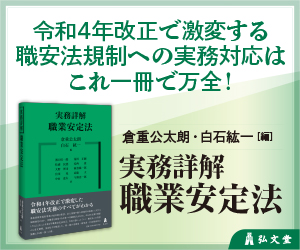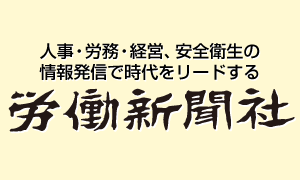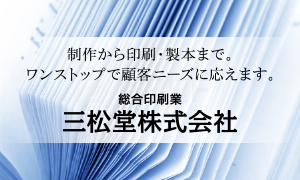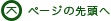生月島はなぜ“除外”されたのか
 著者・広野 真嗣
著者・広野 真嗣
小学館、定価1500円+税
今年6月、日本の「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」が世界遺産に登録された。幕末に建てられた大浦天主堂(国宝)をはじめ、長崎、熊本両県にまたがる12の構成資産が対象だが、その中に、かくれキリシタンのメッカともいえる生月島は入っていない。長崎県が世界遺産登録をめざして作成したPRパンフでは、2014年当時に作ったものには載っていたが、17年作成のものでは消えていた。本書は、著者がこの謎解きに挑戦したルポだ。
江戸幕府成立前後のキリシタン弾圧は有名だが、2世紀半を経た復活劇も、これまたよく知られる。ただ、2世紀半もの潜伏期に、カトリックの教義や儀式を教える宣教師はなく、信者自身による口伝えが繰り返されたため、信仰のスタイルが変質してしまい、明治以降に教会に入会した隠れ信者だけが「復活」の対象になったようだ。
その意味で、生月島のかくれキリシタンの信仰は、仏教などと融合し、漁業生活などの生業と一体化した土俗信仰的な色彩を濃くしている。明治期以降、もはや「隠れる」必要はなくなったにもかかわらず、彼らは教会の復帰の呼び掛けにも応じなかった。
著者は、生月島に足を運んで信者や地元学芸員や研究者らから聞き取りを重ね、今回、なぜ生月島だけが「黙殺」されたのか、事実関係を掘り起こしていく。そして、この島の信仰が、思いもよらぬ方向から消滅に向かっていることも。宗教とはなにか、正当な信仰とはなにか。本書が発する問いは、かつて遠藤周作が「沈黙」で表した問い掛けとは別な角度から、読む者に迫る。 (俊)