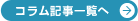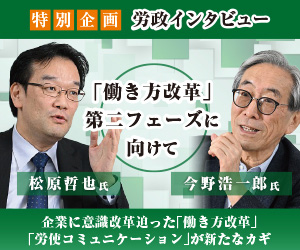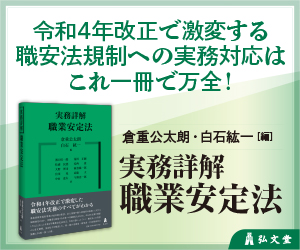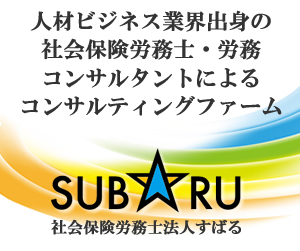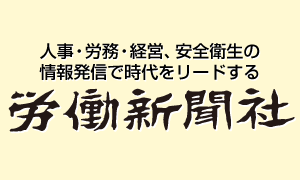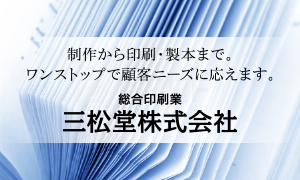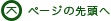Q 今年の育児・介護休業法の改正のうち、4月1日施行の介護関係の改正項目は、どのような内容でしょうか。
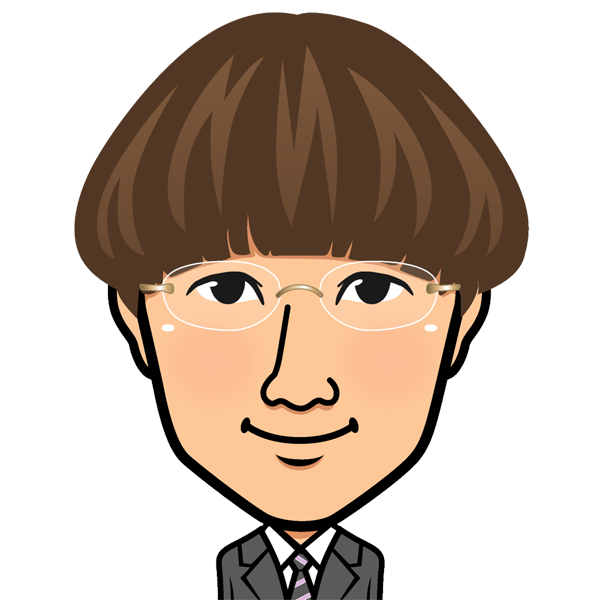 A 育児・介護休業法の改正では、育児関係とともに介護関係の改正項目も数多くありますので、まずは横断的に理解していくことが大切でしょう。
A 育児・介護休業法の改正では、育児関係とともに介護関係の改正項目も数多くありますので、まずは横断的に理解していくことが大切でしょう。
(1)介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
介護休暇とは、労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族の介護や世話をするための休暇のことをいいます。事業主は、労使協定の締結により、一定範囲の労働者を介護休暇の適用対象外とすることができますが、①週の所定労働日数が2日以下、②継続雇用期間6か月未満の要件のうち、②が撤廃され、①週の所定労働日数が2日以下に限定されることになりました。勤続6か月未満の労働者を介護休暇の対象外としていた場合には、労使協定や就業規則などの関連規定の見直しによって、改正法にあわせて勤続6か月未満の労働者も介護休暇を取得できるようにしなければなりません。

(2)介護離職防止のための雇用環境整備
改正法では、深刻化する介護離職への対応などを目的として、介護休業や「介護両立支援制度等」(介護休暇に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、時間外労働の制限に関する制度、深夜業の制限に関する制度、介護のための所定労働時間の短縮等の措置)の申し出が円滑に行われるようにするための雇用環境整備が義務づけられました。事業主は、雇用環境整備として、以下の選択肢のいずれかを行うことが必要であり、現に介護に直面している従業員がおらず、採用する予定がない場合も同様となります。なお両立指針では、これらのうち、可能な限り複数の措置を行うことが望ましいとされています。厚労省の規定例では、②介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口の設置)を選択した場合の周知例が紹介されていますので、何から始めたらよいか迷う場合は参考にしたいものです。
②介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
(3)介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
介護に直面した旨の申し出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項を周知するとともに、介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を行わなければなりません。個別周知・意向確認の方法は、①面談(オンラインも可)、②書面交付、③FAX、④電子メール等(書面に出力できるものに限る)のいずれかとなり、③④は労働者が希望した場合のみ認められます。事業主としては意向確認のための働きかけを行えば足り、申し出の方法については口頭でも可能ですが、取得や利用を控えさせるように誘導するような形態での個別周知や意向確認は認められません。
②介護休業・介護両立支援制度等の申し出先(例:人事部など)
③介護休業給付金に関すること
また、労働者が介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供によって、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は、①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等、②介護休業・介護両立支援制度等の申し出先、③介護休業給付金に関することについて、情報提供しなければなりません。情報提供の方法は、面談(オンラインを含む)、書面の交付、FAX、電子メール等のいずれも選択できます。介護離職防止のための個別の周知・意向確認等とは異なり必ずしも個別に行う必要はありませんが、従業員側からの働きかけがなくても、事業主から積極的に情報提供を行う必要があります。
(小岩 広宣/社会保険労務士法人ナデック 代表社員)