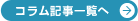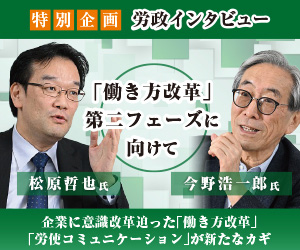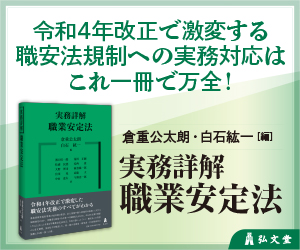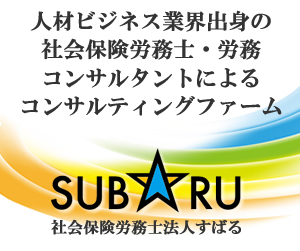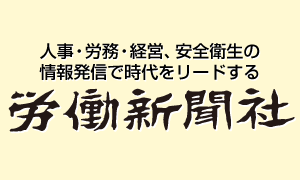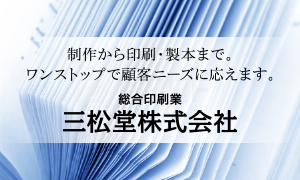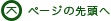Q 来年度の最低賃金が続々と発表されていると聞きますが、最新情報を教えてください。
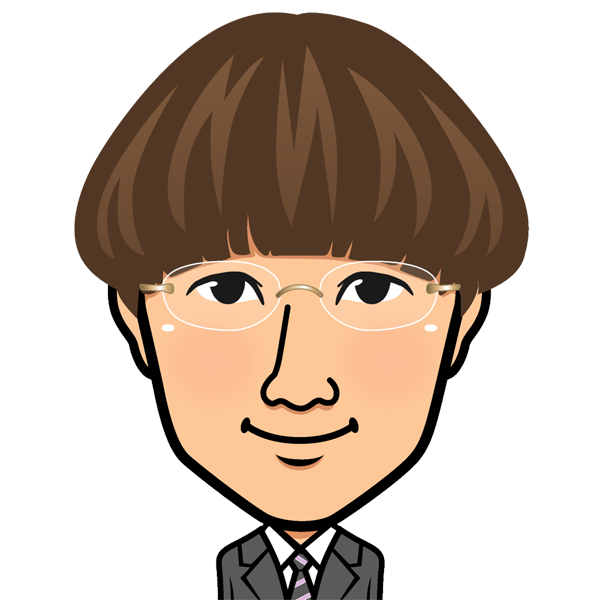 A 前回は、中央最低賃金審議会が答申した地域別最低賃金額改定の目安を受けて、地方最低賃金審議会の答申を経て、都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定・公表している現状について触れました。引き上げ額は鳥取が「+73円」の1030円で最高額であり、発効月日については奈良が「11月16日」、三重が「11月21日」とされているのが目を引きましたが、今回はさらなる続報についてお伝えします。
A 前回は、中央最低賃金審議会が答申した地域別最低賃金額改定の目安を受けて、地方最低賃金審議会の答申を経て、都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定・公表している現状について触れました。引き上げ額は鳥取が「+73円」の1030円で最高額であり、発効月日については奈良が「11月16日」、三重が「11月21日」とされているのが目を引きましたが、今回はさらなる続報についてお伝えします。
引き上げ額については、全都道府県で最低賃金が最も低かった秋田が「+80円」の1031円で最高額となり、中央最低賃金審議会の答申の目安(Cランク、64円)より16円上乗せであり、引き上げ率は約8.4%ということで話題になっています。発効月日については、同じく秋田が来年3月31日、群馬は3月1日と発表されており、従来は10月初旬の適用が通例であり、11月にずれ込む地域があるのが注目されたところ、年をまたいで年度末にまで持ち越されるのはかなり異例です。
最低賃金の改定は通常、毎年10月1日から中旬頃に適用されるのが通例ですが、ここまで地域によって適用時期がばらつき、年をまたぐケースまであるのはかなり特殊だといえます。地方最低賃金審議会での審議・答申、異議申出の手続きを経て、都道府県労働局長により決定される過程で、過去最高水準に引き上げるにあたってのそれぞれの地域の実情を踏まえた事情や意見が反映されていると考えられるでしょう。
地域別最低賃金は、都道府県ごとの発効月日から適用されるため、給与計算の締め切りの中途で給与単価が引き上げされることがありますが、この場合は当然ながら新たに発効された最低賃金を下回ることのないよう日を単位として給与単価を設定・確認していくことになります。また、今回のように都道府県ごとに発効月日が10月から翌年3月と半年近くに渡って開いてしまう場合、たとえば本社と支店であっても都道府県が異なることで相当期間に渡って旧最賃と新最賃に適用が分かれてしまうケースもありうるため、十分に注意しなければなりません。
また、派遣労働者については、派遣先の事業場の所在地の最低賃金が適用されるため、派遣元は派遣先の事業場に適用される最低賃金を把握した上で、その額以上の賃金を支払わなければなりません。こちらも今回は発効時期がばらつくことでケースによっては実務担当者の対応や管理に十分注意する必要があると考えられるでしょう。かなり異例づくめの最低賃金となりますが、確実な実務対応につとめていきたいものです。
(小岩 広宣/社会保険労務士法人ナデック 代表社員)