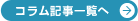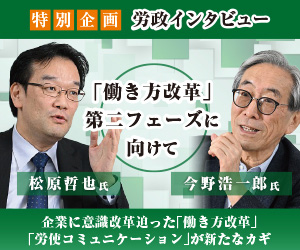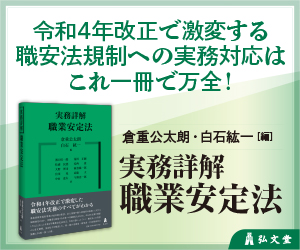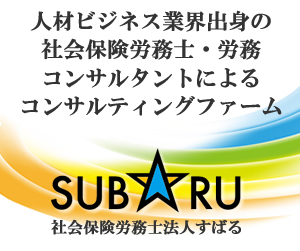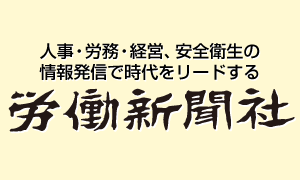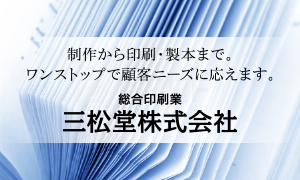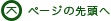Q 女性初の自民党総裁に就任した高市早苗氏の発言で、「ワークライフバランス」という言葉が話題になっていますが、そもそもどのような政策なのでしょうか。
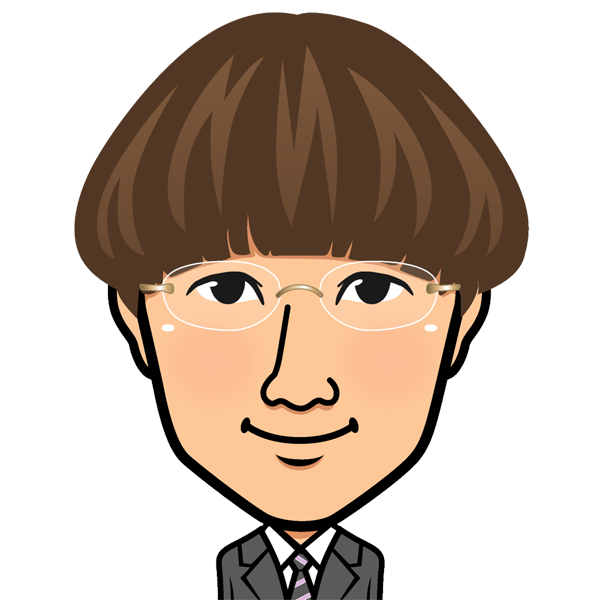 A 10月4日、高市早苗氏が女性初の自民党総裁(第29代)に選出されました。総裁選出後に行われた演説で、「ワークライフバランスという言葉を捨てる」と発言したことが、賛否両論を呼んでいます。メディアでもさまざまな論調がありますが、公正を期すために前後の文脈を以下に引用します。
A 10月4日、高市早苗氏が女性初の自民党総裁(第29代)に選出されました。総裁選出後に行われた演説で、「ワークライフバランスという言葉を捨てる」と発言したことが、賛否両論を呼んでいます。メディアでもさまざまな論調がありますが、公正を期すために前後の文脈を以下に引用します。
たくさんの政策、それもスピーディーに実行しなければいけないこと、たくさんございます。そして、皆様とともに、自民党をですね、もっと気合の入った明るい党にしていく。
多くの方の不安を希望に変える党にしていく。そのための取り組みも必要です。先ほど申し上げました通り、私は約束を守ります。全世代総力結集で、全員参加で頑張らなきゃ立て直せませんよ。
だって今人数少ないですし、もう全員に働いていただきます。馬車馬のように働いていただきます。
私自身もワークライフバランスという言葉を捨てます。働いて働いて働いて働いて働いて、参ります。
皆様にも、ぜひとも日本のために、また自民党を立て直すために、沢山沢山、それぞれの専門分野でお仕事をしていただきますよう心からお願いを申し上げます。
そしてこれから、私はちゃんと謙虚にやってまいりますので、いま「そう」という声が聞こえました。はい。
様々なご指導を賜りますよう、お願いを申し上げます。誠にありがとうございました。(10月4日、自民党総裁選出後の演説)
決選投票で勝利して総裁に選出された直後の演説での発言であり、これから具体的に実行していく政策への思いを表明したというよりは、高揚感に包まれた会場に向けて、率直な言葉で選出への謝辞と今後に向けた決意が熱く語られています。「ワークライフバランスを捨てる」という発言は第一義的には、自分が選出されたからにはリーダーとして全身全霊で課題に当たっていくという決意表明であり、その上で、所属議員たちにそれぞれの得意分野で力を発揮することを求めた趣旨だと理解できます。文脈をみる限りでは、一般的な労働者のワークライフバランスについて否定的な見解を述べ、従来からの政府の政策に修正や変更を求めたものとは理解できないと思われます。
国が推進するワークライフバランスについての政策は、2007年12月にワークライフバランス推進官民トップ会議において、「仕事と生活の調和(ワークライフバランス)憲章」、「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定されたことが始まりであり、その後、政策の進捗や経済情勢の変化などを踏まえて、2010年6月に政労使トップによる合意で新たな「行動指針」が策定されて今日にいたっています。厚生労働省では、憲章及び行動指針などを踏まえて、企業などに対する支援事業が実施され、長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進、仕事と家庭の両立支援などの取り組みが推進されています。
「誰もがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす一方で、子育て・介護の時間や、家庭、地域、自己啓発等にかかる個人の時間を持てる健康で豊かな生活ができるよう、今こそ、社会全体で仕事と生活の双方の調和の実現を希求していかなければならない」とする、「ワークライフバランス憲章」の理念や目的は、すべての労働環境において尊重されるべきであり、このような認識は基本的に社会的に共有されているといえるでしょう。この機会にいま一度、憲章や行動指針の内容に目を通すことで、ワークライフバランスへの理解を深めたいものです。
(小岩 広宣/社会保険労務士法人ナデック 代表社員)