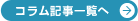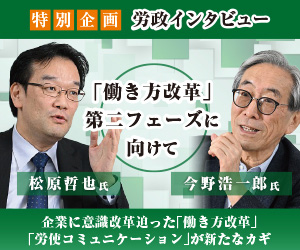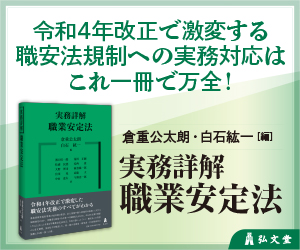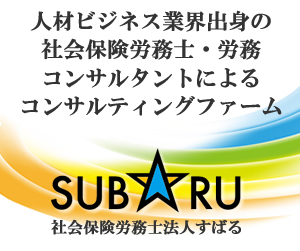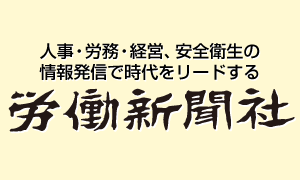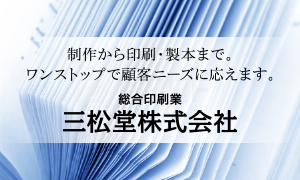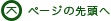Q 若者、障害者、LGBTQなどの多様な人材を戦力にするためには、どのような方策があると考えられますか。
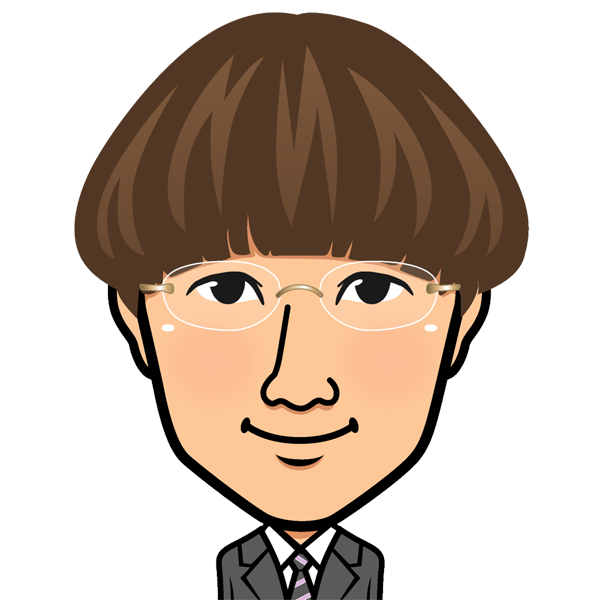 A 前回は、雇用形態別の労務管理についてお伝えしましたが、今回は多様な人材を戦力にするための方策について、簡単に整理します。
A 前回は、雇用形態別の労務管理についてお伝えしましたが、今回は多様な人材を戦力にするための方策について、簡単に整理します。
少子高齢化のさらなる進展と経済活動の複雑化などによって、人材不足への対応はほぼ例外なく優先順位の高い経営テーマになりつつあります。今後は社会的にみてマイノリティとされる人材へのアプローチや働きかけを積極的に行っていくことが、多面的な意味で局面打開につながる可能性があると考えられます。
(1)Z世代について
Z世代は、①自分の生活のペースを守った上で仕事と向き合いたい、②ひとりで仕事を抱え込まずにチームで成果を追いかけたいという特徴を持っています。このような発想や気質は昭和型の職場風土とは相反するケースが少ないことから、採用担当者や上司個人が努力して対応するというよりは、会社全体の意思として向き合うことが大切となります。
応募者に向けて採用計画を発信するにあたっては、労働時間や時間外労働、休日、会社独自の休暇制度といったプライベートの枠組みの確保を明確に訴求し、その上であるべき仕事上の役割や魅力、責任の程度などを深掘りしていく順序で取り組むようにします。ワークライフバランスについて意識することは、必ずしも労働者の利己主義を煽るものではなく、むしろ本音で職場と向き合う基盤となると考えるべきです。
入社後の労務管理については、徹底して本人が職場で孤立しないための取り組みを実践します。上司や先輩が一挙手一投足に介入するのは逆効果だと思われがちですが、あくまでオンライン上の常時管理というスタイルをとれば、デジタルリテラシーが高い世代の感覚にもマッチした信頼感や安心感を培うことができます。その上で、褒めるのも責めるのも、チーム単位でというのが、Z世代への効果的な対処法となります。
(2)障害者について
障害者の採用を考える上で一番のポイントは、それぞれの人が抱えている障害特性を正確に理解することです。まずは、該当する人を採用するかどうかは別として、職場において正しい知識と理解を共有するための研修や周知の取り組みが必須となります。
障害者の労務管理を考える上では、障害特性の中でパフォーマンスを発揮しうる作業や役割をマッチングして、温かく見守り育てる姿勢をつくること、障害特性とは別にその人ならではの個性や能力を見出して、ひとりの人間としてその資質を伸ばすことを援助する取り組みが重要です。とりわけ、後者はあまり認識されていないことから、かえって具体的な成果につながりやすいといえます。
体調面やメンタル面の変化について現場で細かな目配せをしたり、定期の通院や体調不良時などに柔軟に対応できる労働時間、休暇制度などが求められますが、同時に本人理解のための日報や個別面談、コミュニケーションの仕組みづくりも大切だといえるでしょう。
(3)LGBTQについて
いわゆるLGBTQの人の採用や労務管理を考える上での課題は、労働者本人の身体的特徴、価値観や行動類型が広い意味での業務に支障をきたす可能性がある点、職場や取引先、その他の人間関係などを取り巻く社会通念、組織風土や価値観などが、本人を正当に受容しがたい側面がある点です。双方は関連し合っているケースが多いものの、実務的には切り分けて対処していくことが求められます。
採用については、あくまで求められる業務上の資質や能力という視点から、公正かつ客観的な採用選考を進めるべきであり、過剰に意識して警戒を払ったり、逆に過大に要望を受け入れて特別視する必要はありません。圧倒的に多くのマイノリティは何の問題もなく普通に就業しているという理解を基盤として、広く個性を受け入れ認め合うというトップメッセージを発信することが大切だといえるでしょう。
労務管理にあたっては、トイレや更衣室の利用などが論点になりがちですが、実情に即した取り扱いが求められるとはいえ、現場の視点で重要なのは、多様な価値観を認め合うための職場風土づくりだといえます。女性活躍推進の方策の一環として、性差やさまざまな個性にとらわれず、あくまで同じ人間として職務に邁進できる自由で開かれた職場環境を目指すことが、LGBTQにとっても働きやすい環境に近づくものだと考えられます。
(小岩 広宣/社会保険労務士法人ナデック 代表社員)