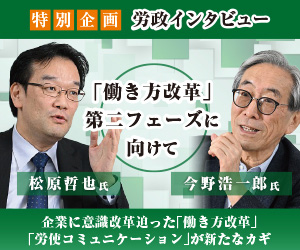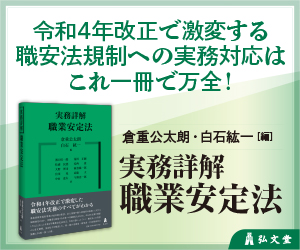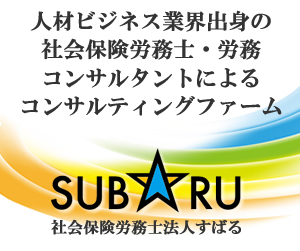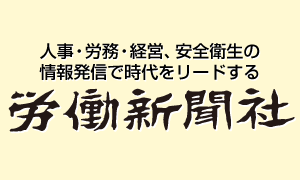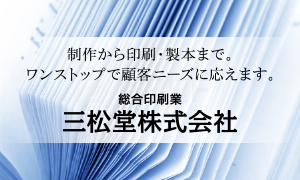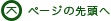賃金の伸び悩みが著しい。官民挙げて取り組んでいる「大幅賃上げ」も物価上昇に追い付かず、統計を見る限り実質賃金はゼロ近辺を上下する"ひ弱さ"が目立つ。労働組合は来年の春闘で今年並みの大幅賃上げを目指しているが、問題はその恩恵を受けにくい多数の中小企業の苦境だ。(報道局)
厚生労働省の毎月勤労統計調査によると、2024年の現金給与総額は名目賃金が1月から4月までは1%台の低い伸びだったが、5月以降は春闘の賃上げやボーナス効果が現れ、2~4%台に伸びた。21年以降、賃金自体は低レベルながらもプラスで推移している。
しかし、名目から物価上昇率を引いた実質賃金になると、依然としてマイナス基調から抜け出せていない。今年6月に1.1%、7月に0.3%と2年半ぶりにプラス転換したものの、8、9、10月と3カ月連続でマイナスに戻ってしまった。プラス転換したのはボーナス増が主要因で、月例賃金だけの伸びでは物価上昇に追い付かない実態が浮かび上がっている。
とりわけ、中小企業の賃金が伸びていない。マイナスに戻った8月の場合、実質賃金ベースでみると、従業員30人以上企業の伸びはマイナス0.4%だが、同5人以上に広げるとマイナス0.8%に拡大。それが、9月にはプラス0.2%とマイナス0.4%に分かれた。中堅企業以上はプラス転換したが、中小零細企業はマイナスのままで、全体もマイナスになった。中小零細企業の賃金が思うように伸びていないのは明らかだ。

東京・有楽町で持続的な「賃上げ」を訴える
連合の芳野友子会長(中央)=2024年3月1日
連合の集計では、今年の春闘では平均1万5281円、5.10%の賃上げを実現した。23年の3.58%をさらに上回る伸び率で、長年、2%台で低迷していた賃上げに弾みを付けた。ただ、これは22年春から始まったロシアによるウクライナ侵攻で輸入物価が急騰し、消費者物価(生鮮食品を除く)に波及して22年が2.3%、23年が3.1%上昇。24年も2%台半ばで推移するなど、物価を賃金が"後追い"しているのが実態だ。
また、物価上昇のコスト増を製品・サービス価格に転嫁しようとしても、大企業の下請けが多い中小企業は思うように転嫁できていない。帝国データバンクが8月に発表した調査によると、価格転嫁できている企業の割合は78%に上ったものの、転嫁率になると平均45%とコスト上昇の半分は転嫁できていないことがわかった。
このため、厚労省や公正取引委員会などは大企業を中心に「適正な価格転嫁」を指導しており、下請法違反の企業を摘発したり、下請けに不合理な価格交渉をしない「パートナーシップ宣言」に加わる企業には税優遇するなど、アメとムチの政策で中小の賃上げを後押ししている。
不十分な「価格転嫁」、倒産も増加
中小側にも深刻な事情がある。24年は最低賃金が平均5.1%アップの1055円になったうえ、慢性的な人手不足で賃金を上げないと人材確保が困難なため。このため、業績以上に賃金を上げる「防衛的賃上げ」に踏み切る企業が相次ぎ、日本商工会議所によると今年は6割に上った。
しかし、それでも台所事情の厳しい中小が増えており、24年度上半期の企業倒産は5095件と10年ぶりに5000件台を突破。そのうち、負債1億円未満の倒産が3830件の75%を占めている(東京商工リサーチ調べ)。コロナ下の資金繰り支援として効力を発揮した「ゼロゼロ融資」の返済が重荷になっているところへ、価格転嫁が思うに任せず行き詰まるケースが増えているのだ。
連合は2025年春闘の賃上げ目標を...
※こちらの記事の全文は、有料会員限定の配信とさせていただいております。有料会員への入会をご検討の方は、右上の「会員限定メールサービス(triangle)」のバナーをクリックしていただき、まずはサンプルをご請求ください。「triangle」は法人向けのサービスです。