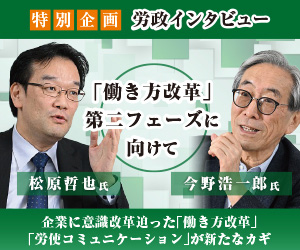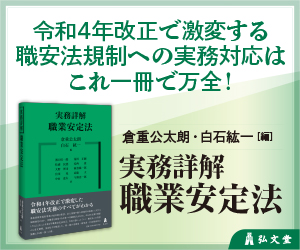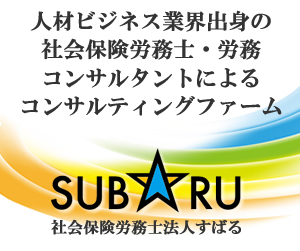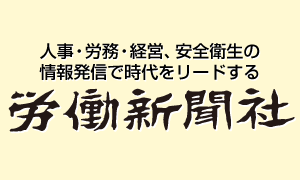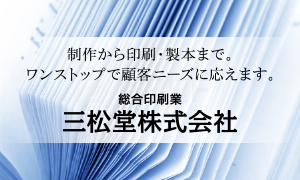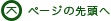労働政策研究・研修機構の第140回労働政策フォーラムがこのほど開かれた。今回は「健康格差社会とミドル・シニアのウェルビーイング(幸福・健康)」がテーマ。
オンデマンドで、千葉大学予防医学センターの近藤克則特任教授が「健康格差社会を生き抜く」と題して基調講演。国内自治体の高齢者約22万人を対象にした追跡調査などを基に、所得とうつ状態の関係や幸福感の決定要因などを解説。労働面では現役時代の「職業性ストレス」、退職後は「社会とのつながり」の有無が健康面や幸福感に影響を及ぼすとの調査結果を披露した。
同機構の高見具広主任研究員は「中年をどう生きるか~健康、仕事、生きがい」と題して、延べ5回に及ぶパネル調査結果を報告した。健康面では、男性が高コレステロールなどの生活習慣病、女性は頭痛や睡眠障害などの更年期症状が多かった。また、生活習慣病は長時間労働、夜勤、シフト勤務などによっても生じる可能性が高く、これらを改善することによって「幸福度」を上げることが可能なことを示唆した。
9月5日のパネルディスカッションでは、都健康長寿医療センター研究所の藤原佳典副所長と日本総研創発戦略センターの小島明子氏が参加。藤原氏は、シニアの就労がフレイル(加齢による心身の衰え)予防につながる調査結果を披露、高齢者施設の「介護助手」を例に挙げて解説した。小島氏は、現役時代から副業・兼業を進めることを推奨し、シニアに向いている就労形態として、近年注目されている「労働者協同組合」を挙げた。