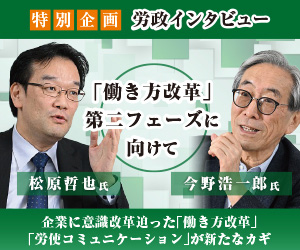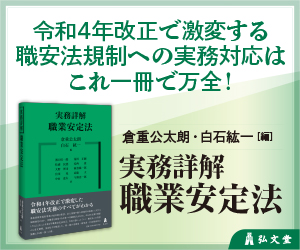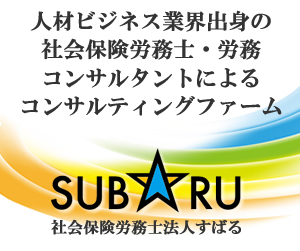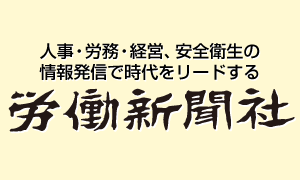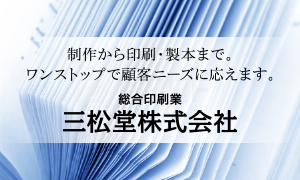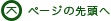労働政策研究・研修機構の第139回労働政策フォーラム「多様化する若者の初期キャリアの現在」が18、24日、オンラインで開かれた。大学生の就職活動などで見られる学生、保護者、企業の間のさまざまなギャップについて着目、議論した。
18日は、同機構の池田心豪・副統括研究員が「親子で考える就職とキャリア」と題して基調報告。新進IT企業を志望する子供と「大企業の安定」を重視する親という典型例を挙げ、なぜ違いが生じるのか課題提起。「大企業の安定」は戦後高度成長期の第2次産業(製造業)によって定着した制度であり、平成不況以降は第3次産業(サービス業)の雇用力が伸び続けている事実などを解説した。
また、同機構の岩脇千裕・主任研究員が「脱工業化と若者のキャリア」と題して研究成果を披露。産業種類を、従来型(製造業と流通などの関連サービス)、脱工業化以降のビジネスサービス(金融など)、社会サービス(福祉分野など)、消費者サービス(外食など)の5タイプに分類し、男女別、賃金、労働時間、訓練などについて比較した。
その結果、①人口減少による若者の売り手市場化②脱工業化に伴う労働の二極化③産業ごとに異なる若者のキャリア、の三つの大きな変化があるとして、企業による雇用管理の改善や「やり直しの効く柔軟社会」の構築などを提言した。
24日のパネルディスカッションではマイナビの長谷川洋介・キャリアリサーチラボ研究員と実践女子大の深澤晶久教授らが加わった。長谷川氏は、就活における親子の世代間ギャップについて経済状況、ワークスタイル、親離れ・子離れの三つを挙げたうえで、近年は学生が親に相談することが増えている事実を紹介。深澤氏は同大で実施している「キャリア教育」の内容を説明した。ただ、親が我が子に望むのは「安定」が最大で、産業構造が変化してもこちらは容易に変化しないことが随所にうかがわれた。