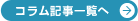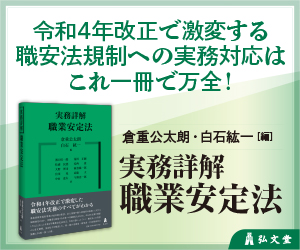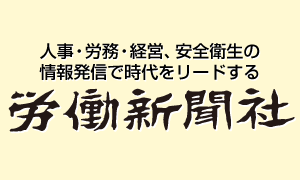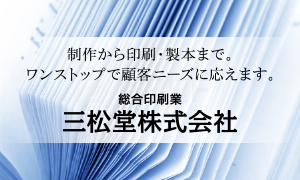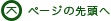「国立」大学でなくなった日の奮闘記
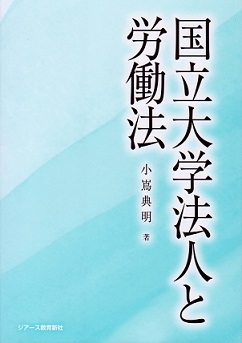 著者・小嶌 典明
著者・小嶌 典明
ジアース教育新社、定価2200円+税
2004年4月、国立大学が独立行政法人の一つである国立大学法人となり、適用される法律も国家公務員法や人事院規則から労働基準法、労働契約法などに“民営化”された。法学者の著者は、その変わり目に大阪大学に在籍、教授として教育研究に携わる一方、人事労務担当として法的な環境整備に尽力したもので、本書はその貴重な記録集。
著者によると、移行に伴って参考にした労働法テキストの「使用者」を「国立大学法人」に置き換えればそのまま使えるかというと、とんでもない話。例えば、企業と同様に労基法に基づく「就業規則」を作成しなければならないが、これが難題。従来は公務員法などにすべてお任せで済んだものが、給与、休暇、昇格、退職、有期契約といった基本的な事柄について、労基法など法的枠組みの範囲内で自ら決めなければならない。加えて、規則案を労働組合と協議する際には、学内の少数組合も相手にしなければならず、苦労した様子がうかがえる。
しかし、病欠時の給与、有給休暇の扱い、昇格や降格など、従来の公務員優遇は想像に絶するものがあり、法人化によってそれらがあぶり出されたのは皮肉ではある。コスト意識なし、競争なし、倒産なしの超安定世界では経営効率化の発想自体がなく、「公僕」意識も失って不思議はない。法人化後も、教職員は「みなし公務員」として扱われ、給与なども「運営費交付金」という名の税金が、減少しているとはいえ潤沢に投入されている。国立大学の授業料が私立大学より低いのはそのお陰だが。
本書は法律学者の“悪戦苦闘”ぶりの記録であり、内容も国立大学に関連した法律実務に限定された一般向けの書ではない。しかし、世の目に触れることが少なかった「公務員の常識は社会の非常識」を浮かび上がらせる興味深い事例が多く、それをあえて書き残した著者の強い良心を感じさせる。 (のり)