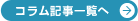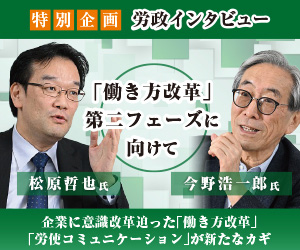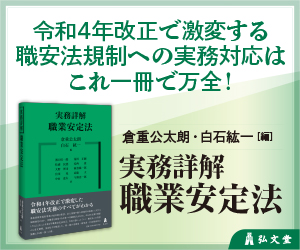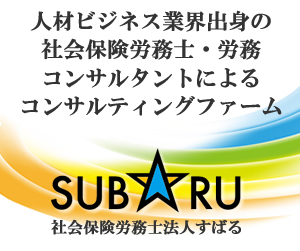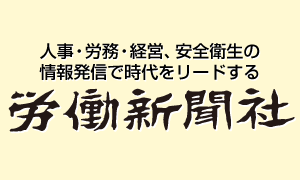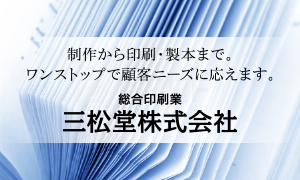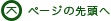Q いわゆる退職代行サービスを用いた従業員に対して、会社側の対応としてはどのような点に留意すべきでしょうか。
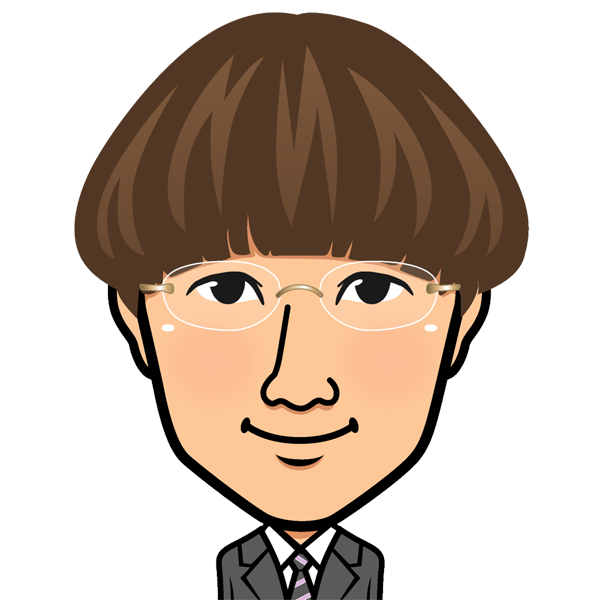 A 「5月病」はもう死語になったという人もいますが、実際には5月に退職したり退職を検討する人は多く、仕事が理由で体調を崩して病院を受診する人も少なくないようです。5月のゴールデンウイーク明けには、労働者が新しい環境の変化についていけずに無気力になったり、眠れなくなったりして体調を悪化する事例も多いとして、各地の自治体や医師会なども注意喚起を促しています。5月病は正式な医学用語ではありませんが、連休明けに身体のだるさ、頭痛、腹痛、不眠、食欲不振、モチベーションの低下などが現れて、適応障害を起こしたり、軽度のうつ症状に陥ってしまう人も一定の頻度で存在するのが現実です。
A 「5月病」はもう死語になったという人もいますが、実際には5月に退職したり退職を検討する人は多く、仕事が理由で体調を崩して病院を受診する人も少なくないようです。5月のゴールデンウイーク明けには、労働者が新しい環境の変化についていけずに無気力になったり、眠れなくなったりして体調を悪化する事例も多いとして、各地の自治体や医師会なども注意喚起を促しています。5月病は正式な医学用語ではありませんが、連休明けに身体のだるさ、頭痛、腹痛、不眠、食欲不振、モチベーションの低下などが現れて、適応障害を起こしたり、軽度のうつ症状に陥ってしまう人も一定の頻度で存在するのが現実です。
さらに最近はいわゆる「退職代行サービス」を利用して退職をはかる人も増えており、ある報道によれば、新卒社員の退職代行サービス利用者は5月が最も多く、特にゴールデンウイーク明けに依頼が増える傾向があるといいます。このようなサービスは、正社員1人あたりの利用料が1万5000~3万円程度と弁護士事務所に依頼する平均的な料金よりも定額なことや、スマホから気軽に依頼できて誰ともリアルに会わずに退職手続きが完結することから、人対人のコミュニケーションや交渉事を避けたがる傾向が強い最近の若者のニーズにかなっているといわれます。
従業員が退職代行サービスを用いて退職を申し出たときは、会社側はどのような対応をとるべきでしょうか。ひとことで退職代行サービスといっても、さまざまな形態があります。退職の手続きにあたって、本人の意思を伝えるだけでなく、退職金や退職の条件などについて会社と交渉するような場合は、弁護士法によって弁護士以外が代理することは禁止されていますし、労働組合でない組織が、労働条件などについて会社と団体交渉を行うことは、労働組合法によって禁止されています。サービス運営会社の主体がどこかを確認し、弁護士や労働組合との提携をうたっている場合であっても、できるかぎりその実態を把握することが大切でしょう。
本人の退職の意思を受けたときの会社側の対応としてもっとも不適切なのは、感情的になって本人に連絡を取ろうとしたり、退職の意思自体を否定するような言動をとったり、本人の勤務期間中の過失などについて損害賠償を請求するような動きを起こすことです。突然本人が出社拒否をして見ず知らずの団体から連絡があったら、上司や担当者としては困惑を隠せず思わず感情的になるのも無理からぬことかもしれませんが、今は退職代行サービスも決してめずらしくない時代だと認識して、努めて冷静に対処することが肝心です。退職の意思が示された以上は、とにかく円満に協力的に手続きを進めることによって、外部からの風評被害や同様のサービスを用いた退職の連鎖を最小限に抑えることができるでしょう。
退職代行サービスの存在は、会社側からすれば目障りに思うかもしれませんが、メリットもなくはありません。本人の委任を受けた専門家なり団体なりが代行して退職の手続きが進められることで、退職の意思が揺らいでなかなか退職日が確定できなかったり、状況によって退職の意思が覆されるといった不安定な展開を防ぐことができる効果もあります。会社側としては、粛々と退職に向けた手続きを踏むことで、次に向けた実務へといち早く気持ちを切り替え、退職から人員の補充、交代への時間と労力のロスを最小化することを目指すべきでしょう。
(小岩 広宣/社会保険労務士法人ナデック 代表社員)