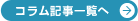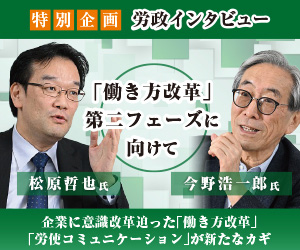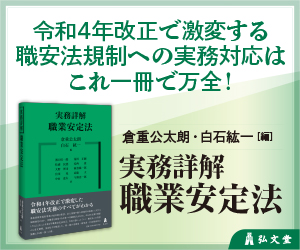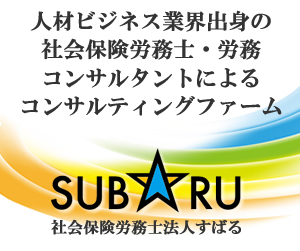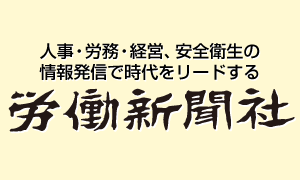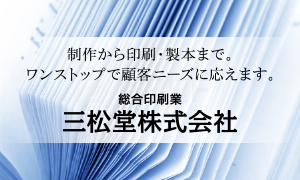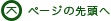Q 新たに高市早苗政権が発足しましたが、これからの労働法制や社会保障制度にはどのような影響があるとみられますか。
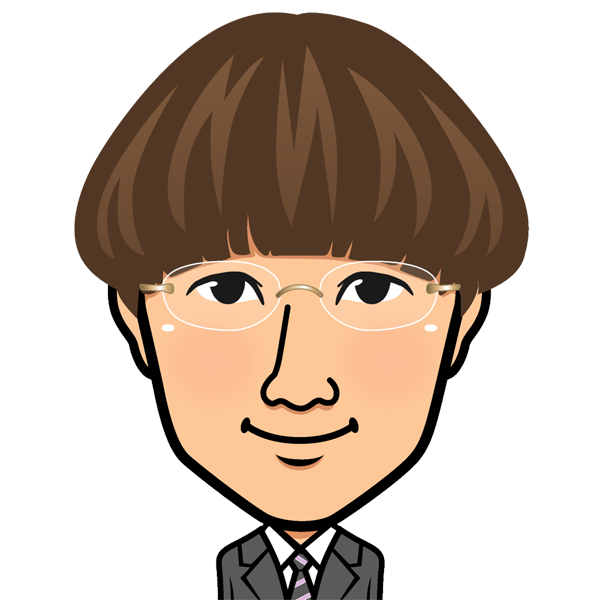 A 10月21日、高市早苗氏が第104代内閣総理大臣に任命され、高市内閣が発足しました。日本初の女性の首相が誕生し、連日のように各方面で話題が飛び交っています。国民生活や就業の根幹にかかわる労働法制、社会保障制度は継続性の中で運営されていくのが通例ですが、行政府の長である首相の指導力やポリシーによって政策の方向性や予算の配分などが大きく影響することもあります。近年では、第二次安倍晋三政権における働き方改革などはその典型だといえます。
A 10月21日、高市早苗氏が第104代内閣総理大臣に任命され、高市内閣が発足しました。日本初の女性の首相が誕生し、連日のように各方面で話題が飛び交っています。国民生活や就業の根幹にかかわる労働法制、社会保障制度は継続性の中で運営されていくのが通例ですが、行政府の長である首相の指導力やポリシーによって政策の方向性や予算の配分などが大きく影響することもあります。近年では、第二次安倍晋三政権における働き方改革などはその典型だといえます。
政権発足時の基本方針(閣議決定)では、①強い経済の実現、②地方を伸ばし、暮らしを守る、③外交力と防衛力の強化が3つの柱とされ、①では「健康医療安全保障の構築」「人材総活躍の環境づくり」、②では「外国人問題に関する司令塔機能の強化、総合的な対策」が盛り込まれています。これらの点は、今後の政策全般の基本的な理念、フレームとなっていくと思われます。
上野賢一郎厚生労働大臣への指示書では、具体的に9項目の内容が盛り込まれており、とりわけ社会保障の一体改革や多様な働き方の促進などに力点がおかれていますが、労働時間規制の緩和のテーマがメディアなどでも大きく取り上げられています。以下に主に労働政策に関する部分を抜粋します。
(5)関係大臣と協力して、働き方改革を推進するとともに、多様な働き方を踏まえたルール整備を図ることで、安心して働くことができる環境を整備する。関係大臣と協力して、高齢者・女性・障害者・外国人の就労促進など、支え手を最大限増やす取組を進める。
(6)関係大臣と協力して、就職氷河期世代の就労や社会参加への支援、高齢期を見据えた支援を着実に実施する。
労働時間規制(時間外労働の上限規制)については、2019年の「働き方改革関連法」で強化・施行されており、一定の要件を満たした場合の上限は「月100時間未満、年720時間」とされていますが、上野厚生労働大臣は就任挨拶で「心身の健康維持と従業者の選択を前提にした労働時間規制の緩和の検討を行う」と表明し、規制緩和に向けた方向を打ち出しています。
付加価値を高める労働への転換、リスキリングやデジタル技術の活用の推進、兼業・副業の促進、最低賃金の引上げの加速、働き方改革の推進、多様な働き方を踏まえたルール整備などと並行して検討・実施するとされているため、従来の規制強化中心の政策から転換を図り、経済成長重視の規制緩和へと変化していく方向性をみることができます。
なお、社会保障関連のテーマとしては、現段階では政府としての見解ではないものの、10月20日の自民党・日本維新の会の連立政権合意文書の中で、「配偶者の社会保険加入率上昇及び生涯非婚率上昇等をも踏まえた第三号被保険者制度等の見直し」にも触れられています。これらの点が今後どのように議論されていくのかについても、注視していきたいものです。
(小岩 広宣/社会保険労務士法人ナデック 代表社員)