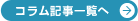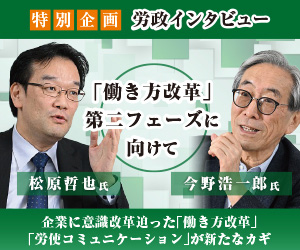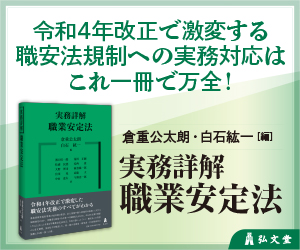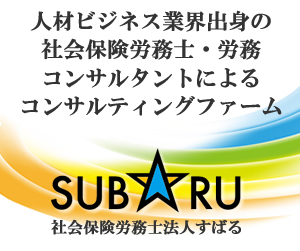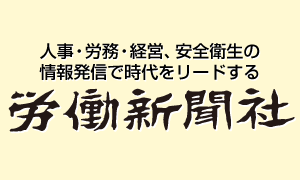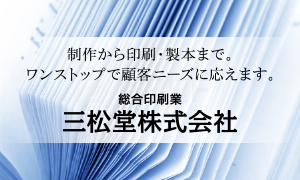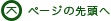Q 契約社員、パートタイマー、アルバイト、派遣社員、請負・委託などによって、労務管理にはどのような違いがありますか。
A 前回は、雇用形態別の採用フローについてお伝えしましたが、今回は雇用形態別の労務管理について、簡単に整理します。
契約社員・パート・アルバイトの労務管理のポイント
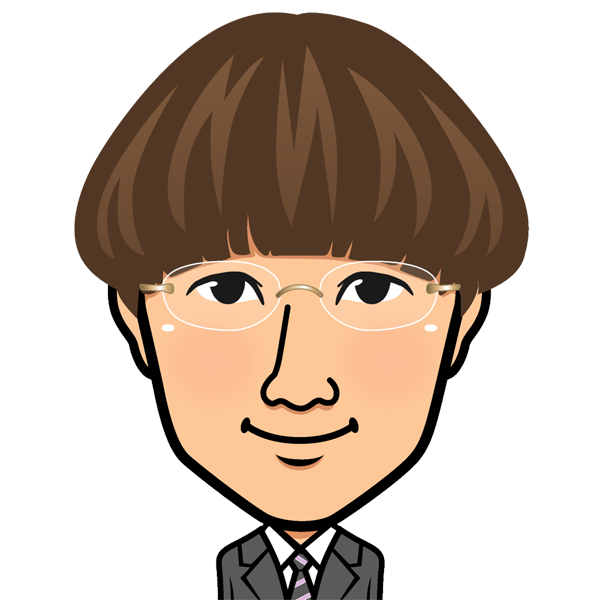 いずれも非正規雇用の類型である、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの労務管理のあり方は、基幹となる労働力である正社員を補佐したり補充したりする役割が期待されるという点では、基本的に同様だといえます。一般的に会社からの期待度としては、契約社員>パートタイマー>アルバイトというイメージで理解されることが多いですが、実際の業務上の役割には個別契約や組織運営によって多様なパターンがあります。
いずれも非正規雇用の類型である、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの労務管理のあり方は、基幹となる労働力である正社員を補佐したり補充したりする役割が期待されるという点では、基本的に同様だといえます。一般的に会社からの期待度としては、契約社員>パートタイマー>アルバイトというイメージで理解されることが多いですが、実際の業務上の役割には個別契約や組織運営によって多様なパターンがあります。
契約社員の労務管理で最も留意すべき点は、正社員の業務内容や裁量権限、責任の程度などとの違いを明確にして雇用し、実際の現場における報告・連絡・相談のフローにも反映させていくことです。正社員とのすみ分けが曖昧な場合は同一労働同一賃金の観点からも問題となるだけでなく、正社員のモチベーションへの悪影響、契約社員自身の将来の役割期待への不安や不満にも結びついてしまいがちです。
パートやアルバイトについては、まずもって自社におけるパート、アルバイトの定義と要件を明確にすること、労働時間や出退勤のルールを確立させることが重要です。一般的にパート、アルバイトと呼ばれているものと、具体的にその会社におけるパート、アルバイトの制度とは、同じではないことが多々あります。就業規則における定義規定だけでなく、具体的に共通項と相違点を理解しておくことが必要だといえます。
契約社員、パートタイマー、アルバイトの制度上の労働条件や役割期待については、就業規則や個別契約の記載にとどまらず、社内の周知事項としてすべての関係者が理解できていることが望ましいといえるでしょう。そうすることで、それぞれの所属意識やキャリア構築への意識が明確になり、ひいては労務トラブルなどを事前に予防することにもつながります。
派遣社員・請負・委託契約の労務管理のポイント
派遣社員、請負契約、委託契約は、いずれも自社が雇用する労働者ではありませんから、本来は「労務管理」というとらえ方として対処するのは不適当だといえます。とはいえ、現実にはこれらの労働力は会社の業務運営の奥深くに入り込んで活躍しており、会社の裁量・判断によってマネジメントしていくという視点は不可欠です。
派遣社員に対する業務指揮権は会社(派遣先)が持っているため、実務的には会社はほかの(直接雇用の)労働者と同じように業務上の指示や命令を出すことができます。一方、懲戒権を持っているのは雇用主である派遣元であるため、業務上のミスや非違行為があっても、会社(派遣先)はいっさい制裁などを与えることができません。
派遣社員の労務管理にあたっては、この点についての十分な理解と対処がポイントとなります。実際に就業をめぐる指導や監督と、ミスなどが生じた場合の注意、それらが相次いだ場合の懲戒は、明確な線引きのもとに実施されるというよりは、それぞれの連携の中で作用しているケースが多いといえます。日常的な派遣先と派遣元との信頼関係のパイプを構築して、いざというときに連携して機動的に対応できる準備を怠らないことが求められるといえます。
請負や委託は、そもそも労働者ではありません。あくまで請負契約や委託契約に基づいて、会社が発注し、外部の事業者として業務を処理することから、会社が労働者に対して負うような法律上の義務を求められることはなく、原則的には自由な裁量・権限に委ねられることになります。とはいえ、昨今では請負や委託についても、実態が労働者に近似している形態のものが増加しています。フリーランス新法で求められる書面等による取引条件の明示の徹底をはかるとともに、単なるペーパーによる確認ごとという理解にとどまらず、進捗・管理についてタイムリーに確認しあっていく仕組みづくりが肝要だといえるでしょう。
(小岩 広宣/社会保険労務士法人ナデック 代表社員)