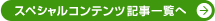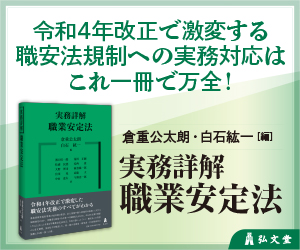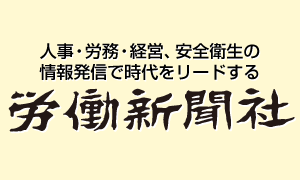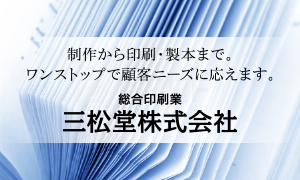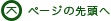5 まとめにかえて――賃金制度の現状と「同一労働同一賃金」
 裁判官も神様ではない。ときには、その判断を誤ることもある。新聞等でも大きく取り上げられた2016年5月13日のN運輸事件=東京地裁判決は、そうした問題のある判決の典型ともいえるものであった。
裁判官も神様ではない。ときには、その判断を誤ることもある。新聞等でも大きく取り上げられた2016年5月13日のN運輸事件=東京地裁判決は、そうした問題のある判決の典型ともいえるものであった。
定年後も同じ仕事なのに、賃下げは違法。マスコミは、このように判決の内容を報道したが、同じことは、定年延長の場合にも起きる。定年延長にせよ、定年後再雇用にせよ、定年後(定年延長の場合は旧定年後)の労働条件は〝白紙〟なのであって、そこに賃下げという要素が入り込む余地はない。わが国の企業は、こうした考え方に立って、これまで定年延長や定年後の再雇用を進めてきたといってよい(注1)。
本件の場合、定年前の労働者(正社員)に適用される労働契約には、期間の定めがなく、定年後再雇用された労働者(嘱託社員)に適用される労働契約には、期間の定めがあった。このようなわが国の企業においてごく普通にみられる状況のもとで、被告=会社は、次のように主張する。
「賃金等の労働条件は、定年退職後の労働契約として新たに設定したものであり、定年後再雇用であることを理由に、正社員との間で労働条件の相違を設けているのであって、『期間の定めがあること』を理由として労働条件の相違を設けているわけではない。したがって、嘱託社員である原告らと正社員との間の労働条件の相違は、『期間の定めがあること』を理由とする労働条件の相違ではないから、本件に労働契約法20条は適用されない」。
例えば、一方に定年が延長された無期契約の正社員がいて、他方に定年後再雇用された有期の嘱託社員がいたとする。いささか想定しにくいケースではあるが、こうしたケースにおいて、労働条件に違いがあるというのであれば、まだ労働契約法20条の適用を論じる余地はある。しかし、この事件は、そんなケースではもちろんなかった。
にもかかわらず、判決は、労働契約法20条の適用範囲については「使用者が期間の定めの有無を理由として労働条件の相違を設けた場合に限定して解すべき根拠は乏しい」とした上で、「当該有期契約労働者と無期契約労働者との間の労働条件の相違が、期間の定めの有無に関連して生じたもの」であればよいとして、次のようにいう。
本件の場合、「有期契約労働者である嘱託社員と無期契約労働者である正社員との間には、賃金の定めについて、その地位の区別に基づく定型的な労働条件の相違があることが認められるのであるから、当該労働条件の相違(本件相違)が期間の定めの有無に関連して生じたものであることは明らかというべきである」。
「したがって、この点に関する被告の主張を採用することはできない」。
労働契約法20条の適用問題については、このように会社の主張を一蹴して終わり。これほど乱暴な議論はみたことがない。それが率直な感想であった。他方、労働契約法20条の解釈においても、判決は驚くべき手法を採用する。パートタイム労働法9条に照らして、その意味を確定するという手法がそれである。
判決は、短時間労働者については、パートタイム労働法9条により、〔1〕職務の内容並びに〔2〕当該職務の内容及び配置の変更の範囲が「通常の労働者と同一である限り、その他の事情を考慮することなく、賃金を含む待遇について差別的取扱いが禁止されている」とした上で、有期契約労働者についても、「職務の内容(上記〔1〕)並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲(上記〔2〕)が無期契約労働者と同一であるにもかかわらず、労働者にとって重要な労働条件である賃金の額について、有期契約労働者と無期契約労働者との間に相違を設けることは、その相違の程度にかかわらず、これを正当と解すべき特段の事情がない限り、不合理であるとの評価を免れない」とする。
そして、判決は、被告における定年後再雇用制度には、賃金コスト圧縮の手段としての側面があり、被告がこのような「賃金コスト圧縮を行わなければならないような財務状況ないし経営状況に置かれていたことを認めるべき証拠」もないとして、こうした事情のもとでは、「定年後再雇用制度を賃金コスト圧縮の手段として用いることまでもが正当であると解することはできない」とした(注2)。
「同一労働同一賃金」の原則に何の疑問も持たず、これを躊躇なく推し進めていくと、このような結果になる。本判決は、このことを暗示しているともいえる。
しかし、「職務の内容」や「配置の変更の範囲」は、正社員と非正社員の間における賃金格差がどの程度であれば認められる(認められない)のかを判断する際の指標とはなっても、賃金それ自体を決定する際の基準とはなっていない、という現実がある。
例えば、多くの企業は、正社員については、賃金カーブが一定年齢までは右肩上がりの曲線を描く「職能給」制度を採用する(注3)一方で、非正社員については、――仕事が変わらない以上、賃金も変わらない――賃金カーブがフラットな構造になる「職務給」制度を採用している。このような状況のもとで、均等待遇=「同一労働同一賃金」を実現することは、およそ不可能に近い。正社員と非正社員双方の勤続年数が長くなればなるほど、むしろ格差は拡大していく。
確かに、勤続年数が短ければ、一方が「職能給」、他方が「職務給」という状況においても、ある程度の待遇の均衡は確保できる(注4)。誰がみても不合理といえる格差については、法律の力で是正を図る。そのこと自体に異論はないものの、これが限度ではないか(注5)。「同一労働同一賃金」をめぐる議論においても、そうした限度を弁えた、冷静な検討が必要といえよう。
注1:定年延長や定年後再雇用の場合には、賃金が相当「ダウン」する。雇用保険法61条以下には、このことを前提とした定めも置かれている。60歳以降の賃金が60歳時点の賃金の75%未満に低下するときに支給される、高年齢雇用継続給付の制度がそれであるが、MAXである15%の給付(正確には60歳以降に支給される賃金の15%)を受けるためには、賃金が60歳時点の賃金に比べ61%以下に低下していることが要件とされる。つまり、制度そのものが4割程度の賃金「ダウン」を想定していることになる(なお、本件の場合、被告の主張するところによれば、定年後再雇用者の賃金は「総支給額が平均して定年前の79パーセント程度になるように考慮して」設定したとされており(その後、組合の要求に応じる形で賃金額はさらに引き上げられた)、そもそも高年齢雇用継続給付の支給対象ではなかったと推測される)。
また、民間企業の再雇用に当たるものとして、公務員には再任用の制度がある。フルタイム勤務の制度もあるが、国家公務員の場合、課長クラス(地方出先機関)で、年収は民間企業のボーナスに相当する期末・勤勉手当込みで390万円程度にとどまる。通勤手当等の諸手当は別途支給されるとはいえ、俸給月額は同じ級(行政職俸給表(一)4級)の平均支給額(定年前の支給額ではない)の約7割、期末・勤勉手当の支給額も、一般の職員に比べ、その約半分に抑えられている(ただし、同一級である以上、職務の内容は変わらない)。
注2:判決は、定年後再雇用された嘱託職員の賃金水準が「新規採用の正社員よりも低く設定」されていたことにも言及しているが、判決自身が一方で「有期契約労働者と無期契約労働者との間に相違を設けることは、その相違の程度にかかわらず、これを正当と解すべき特段の事情がない限り、不合理であるとの評価を免れない」としている以上、このことが結論に影響を与えたというわけではない。
注3:本連載の1でみた、日本経団連「2015年6月度 定期賃金調査結果」も、こうした事実を前提にしなければ、説明できない。
注4:相当数の企業が非正社員の雇用可能期間に上限を設けている理由の一つも、ここにある。この点につき、拙著『国立大学法人と労働法』(ジアース教育新社、2014年)324頁以下を併せ参照。
注5:労働契約法20条やパートタイム労働法8条についても、その程度の訓示規定に近い規定(誰もが不合理と考える格差に限って、これを無効とする私法上の効力を認める)として考えるのが、穏当といえよう。
小嶌 典明氏(こじま・のりあき)1952年大阪市生まれ。神戸大学法学部卒業。大阪大学大学院法学研究科教授。労働法専攻。小渕内閣から第一次安倍内閣まで、規制改革委員会の参与等として雇用・労働法制の改革に従事するかたわら、法人化の前後を通じて計8年間、国立大学における人事労務の現場で実務に携わる。
最近の主な著作に、『職場の法律は小説より奇なり』(講談社)のほか、『労働市場改革のミッション』(東洋経済新報社)、『国立大学法人と労働法』(ジアース教育新社)、『労働法の「常識」は現場の「非常識」――程良い規制を求めて』(中央経済社)、『労働法改革は現場に学べ!――これからの雇用・労働法制』(労働新聞社)、『法人職員・公務員のための労働法72話』(ジアース教育新社)、『労働法とその周辺――神は細部に宿り給ふ』(アドバンスニュース出版)、『メモワール労働者派遣法――歴史を知れば、今がわかる』(同前)がある。