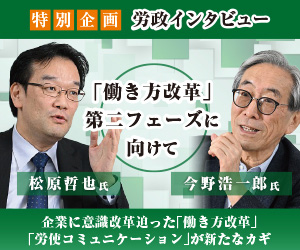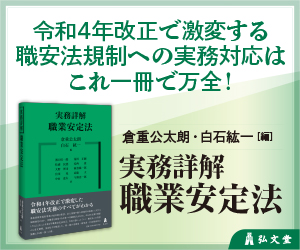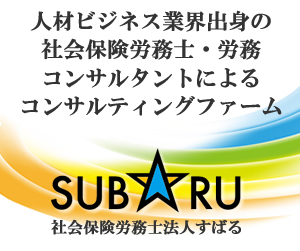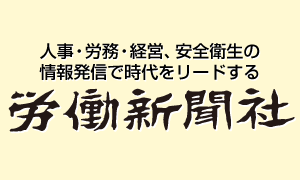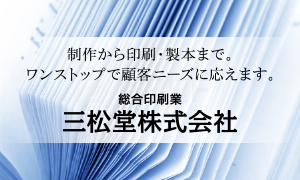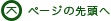物価上昇が賃金上昇を上回る状況が続いている。実質賃金のマイナスは国民生活の水準低下を意味しており、今のところ、消費マインドが好転する兆しは見られない。しかし、肝心な政治が物価・景気対策そっちのけの権力闘争を続けており、それが先行き不安をさらに高める悪循環を生んでいる。(報道局)
厚生労働省の毎月勤労統計調査を見る限り、実質賃金の停滞が鮮明になっている。この7月で名目賃金は43カ月連続でプラスを続けてはいるものの、消費者物価の上昇分を差し引いた実質賃金は今年1月からマイナス続きだ。7月は速報ベースでプラス0.5%とようやくプラス転換したかに見えたが、確報ベースではマイナス0.2%に落ち込み、7カ月連続のマイナスを記録した。
日本経済は実質賃金のマイナスから抜け出せない。2017年から18年、21年以外はマイナス続きで、22年からは3年連続のマイナス。25年も年初からマイナスが続いており、このまま推移すれば4年連続のマイナスという前代未聞の事態になりかねない。
こうした事態に対して、官民挙げての「賃上げ」キャンペーンが展開され、連合によると春闘では2年連続で5%を超える賃上げに成功。最低賃金も政府の強力な後押しで3年連続の大幅底上げが実現し、今年は全都道府県で1000円を超えて平均1121円のレベルにまで引き上げられた。
これらを反映して、国税庁が最近公表した民間給与実態調査でも、24年は平均478万円(前年比3.9%増)となり、伸び率は1991年以来、33年ぶりの高さになった。ここ3年ほど、給与が堅調に伸びていることは間違いない事実だ。ただ、業種別にみると、最高の「電気・ガス・熱供給・水道」の832万円から最低の「宿泊・飲食サービス」の279万円には3倍近い開きがあり、給与水準の「二極化」を示唆している。低賃金の業種は中小・零細企業が多く、賃上げは平均以下という企業が多数を占めている。
一方、物価は賃金以上に上がっている。総務省の消費者物価指数(生鮮食品を除く)の伸びは22年が2.3%、23年が3.1%、24年が2.5%。25年も3%を超える上昇が続いている。7月は2.7%に下がったものの、生鮮品以外の食料は8.0%も上がった。
新米価格は昨年を上回る水準に
食料品価格の上昇は、帝国データバンクの調査でも裏付けられている。食品主要195社の値上げは24年こそやや落ち着きを見せていたものの、25年になると再びラッシュの様相に。1月から11月判明分までの値上げは調味料や加工食品を中心に、2年ぶりに2万品目を超えており、昨年よりすでに7000品目以上多い。
問題となっているコメ価格も、政府の備蓄米放出効果が薄れ、今年の新米は昨年を上回る高値で出回っている。資材や肥料価格の高騰など、生産者側にも事情はあるものの、このままでは消費者の「コメ離れ」がさらに進むことが目に見えている。
国民の肌感覚では、実質賃金がプラス2~3%になれば「豊かさ」をある程度実感できるが、現実はそれとほど遠いまま推移している。日本企業の生産性の低さが要因の一つではあるものの、「史上最高益」に沸く大企業が多く、恩恵がその従業員に限定されていることを考慮すれば、「所得の再分配」政策が改めて重要になりそうだ。
公約宙ぶらりん、政治の無責任
しかし、政府・与党の動きは極めて鈍く、物価高が緊急・最大課題であるにもかかわらず、実質的に何の対策も打っていない。7月の参院選で、自民党は「一律2万円給付」、公明党も「給付と減税セット」を打ち出し、野党側は「消費税などの減税」で対抗した。結果は与党の敗北に終わったが、...
※こちらの記事の全文は、有料会員限定の配信とさせていただいております。有料会員への入会をご検討の方は、右上の「会員限定メールサービス(triangle)」のバナーをクリックしていただき、まずはサンプルをご請求ください。「triangle」は法人向けのサービスです。