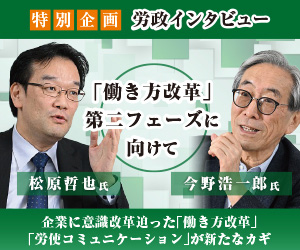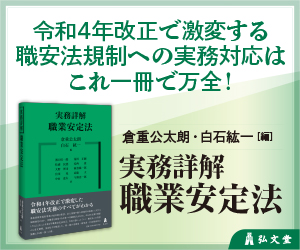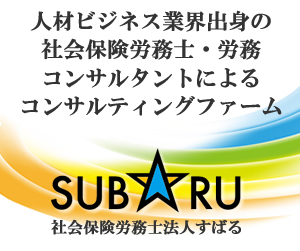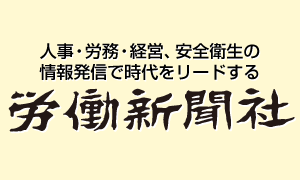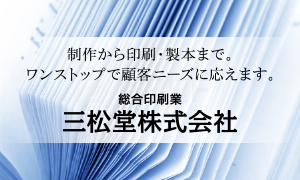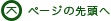公労使と障害者団体の代表らで構成する厚生労働省の第5回「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」(山川隆一座長)は9日、検討テーマのうち、障害者雇用納付金に関して常用労働者100人以下の企業にも納付義務の適用範囲を拡大することの是非について議論した=写真。質の重視と経済的・事務的負担などを理由に慎重な意見があった一方で、適用拡大または周知・準備期間を含めた段階的な適用拡大を求める声が多く聞かれた。
公労使と障害者団体の代表らで構成する厚生労働省の第5回「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」(山川隆一座長)は9日、検討テーマのうち、障害者雇用納付金に関して常用労働者100人以下の企業にも納付義務の適用範囲を拡大することの是非について議論した=写真。質の重視と経済的・事務的負担などを理由に慎重な意見があった一方で、適用拡大または周知・準備期間を含めた段階的な適用拡大を求める声が多く聞かれた。
現在、企業の法定雇用率の未達成企業は「不足分の人数×5万円」の納付金を毎月政府に支払わなければならないが、100人未満の企業は納付金の対象になっておらず、これが「雇用ゼロ企業」が減らないひとつの要因になっている。ただ、納付金は達成企業に対する調整金や報奨金の原資になっているが、未達成は中小企業が多いことから、「資金力の弱い中小企業から裕福な大企業に資金が向かっている」との批判も根強い。
同研究会は昨年12月にスタート。障害者の雇用者数は堅調に増加している一方で「雇用の質」の向上に向けてどのような対応が求められるか。加えて、雇用率制度について(1)手帳を所持していない難病患者や、精神・発達障害者の位置づけ(2)就労継続支援A型事業所やその利用者の位置づけ(3)精神障害者において雇用率制度における「重度」区分を設けることについて(4)納付義務の適用範囲拡大について――などをテーマにヒアリングを交えて議論を深めている。
この日からヒアリングで聞き取ったテーマに沿った個別の議論を始めた格好で、今後も同様の進め方を展開。年内にも報告書を取りまとめる方針で...
※こちらの記事の全文は、有料会員限定の配信とさせていただいております。有料会員への入会をご検討の方は、右上の「会員限定メールサービス(triangle)」のバナーをクリックしていただき、まずはサンプルをご請求ください。「triangle」は法人向けのサービスです。
【関連記事】
「代行ビジネス」に危機感募らす
障害者雇用促進研究会、議論入り(4月14日)