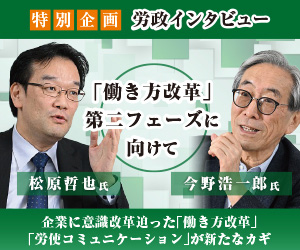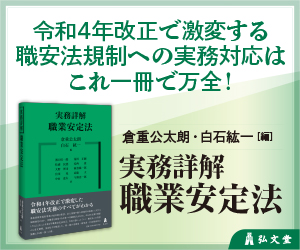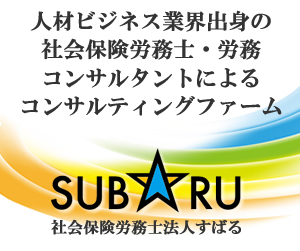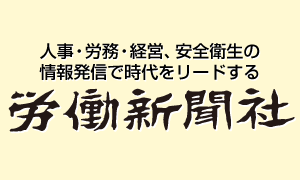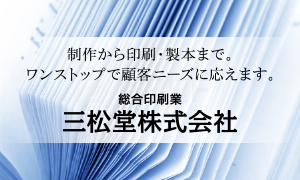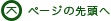公労使と障害者団体の代表らで構成する厚生労働省の第10回「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」(山川隆一座長)は11日、障害者雇用の「質」として重視されるべき要素と、「質」を高めるために取るべき政策的対応を念頭に議論を深めた=写真。また、これまでの議論で課題が指摘されていた「障害者雇用ビジネス」(代行ビジネス)については、業界団体による適正化に向けた動きを把握して検討する形となり、次回会合に日本障害者雇用促進事業者協会(JEAP)を招いて議論を深める予定だ。
公労使と障害者団体の代表らで構成する厚生労働省の第10回「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」(山川隆一座長)は11日、障害者雇用の「質」として重視されるべき要素と、「質」を高めるために取るべき政策的対応を念頭に議論を深めた=写真。また、これまでの議論で課題が指摘されていた「障害者雇用ビジネス」(代行ビジネス)については、業界団体による適正化に向けた動きを把握して検討する形となり、次回会合に日本障害者雇用促進事業者協会(JEAP)を招いて議論を深める予定だ。
昨年12月に始動した同研究会では、障害者の雇用者数は堅調に増加している一方で「雇用の質」の向上に向けてどのような対応が求められるか。また、雇用率制度については(1)手帳を所持していない難病患者や、精神・発達障害者の位置づけ(2)就労継続支援A型事業所やその利用者の位置づけ(3)精神障害者において雇用率制度における「重度」区分を設けることについて(4)障害者雇用納付金の納付義務の適用範囲を常用労働者数が100人以下の事業主へ拡大することについて――をテーマにヒアリングを交えて議論を重ねている。
この日、事務局の厚労省は、2018年以降の法制の流れや関係機関が実施した大規模なアンケートの調査結果、同研究会で挙がった意見を整理したうえで、論点と方向性を提示。障害者雇用の「質」として重視されるべき要素と「質」を高めるために取るべき政策的対応は何か――を念頭に、(1)能力発揮の十分な促進(職務の選定・創出と障害特性等との適切なマッチング・成長を促すOJTや教育訓練機会の確保)、(2)能力発揮の成果の事業活動への十分な活用、(3)発揮した能力に対する正当な評価とその反映――などをガイドラインを含む法令に明示する案を示した。
このほか、「障害者雇用ビジネス」については...
※こちらの記事の全文は、有料会員限定の配信とさせていただいております。有料会員への入会をご検討の方は、右上の「会員限定メールサービス(triangle)」のバナーをクリックしていただき、まずはサンプルをご請求ください。「triangle」は法人向けのサービスです。
【関連記事】
「代行ビジネス」に危機感募らす
障害者雇用促進研究会、議論入り(4月14日)